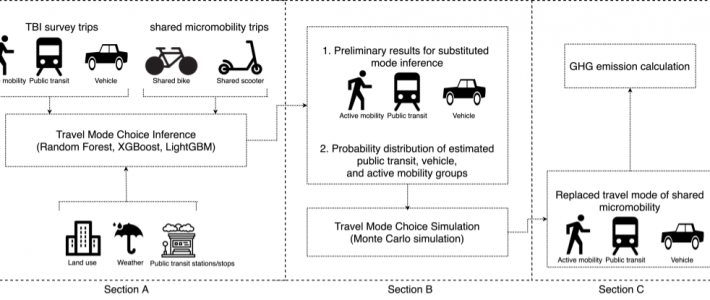【科研費|基盤A】アニマルウェアラブル2.0:野生動物IoTの高速通信・高信頼機構の確立
2021 – 2023年度 概要: 本提案は申請者らが実施中の福島原発事故対応で直面している技術的な課題の解決を目指す野生動物装着センサの研究である。移動する動物にセンサを装着し、行動や周辺環境をモニタリングする構想はセンサネットワーク研究の初期から見られる。ここでの課題は電源・情報・道路・衛星インフラが存在しない高線量空間に生息する小型の哺乳類に対応可能な情報基盤技術の実現である。 研究代表者: 小林 博樹 東京大学, 情報基盤センター, 教授 (60610649) 研究分担者: 瀬崎 薫 東京大学, 空間情報科学研究センター, 教授 (10216541) 西山 勇毅 東京大学, 生産技術研究所, 助教 (80816687) 川瀬 純也 東京大学, 情報基盤センター, 助教 (80872522) 配分機関 日本学術振興会|科学研究費助成事業 関連リンク https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-21H04886/